滅私奉公で、労働集約型の働き方ではなく、
誰もが「知的生産」をしましょう、という本。
| イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」 | |
 | 安宅和人 英治出版 2010-11-24 売り上げランキング : 1301 Amazonで詳しく見る |
こちらです。
根性論に逃げずに
とにかく夜中まで頑張れば、いいものが出来る、という時代じゃ
ないよネ!っていう話。
だって、事業環境はどんどん変化していて
その分、周りの人も、昨日と違うことを考えてたり。
そのあたり、
ある程度「慮る」必要はあれど、あれやこれや考え込みすぎて動けなくなってしまっては
元も子もない。
そのためには、「イシューが何か」を見極める
イシュードリブンで仕事を効率的に進めていきましょう、という指南書です。
これは、本当に理想的な姿であり、
やはり、長時間仕事に打ち込みがちだった私にも参考に出来ることが沢山ありました。
おかげで最近は、
このやり方でよかったのか、今議論している方向はそもそも土俵が違うのではないか、
なんてことを、つねづね、考えたりしています。
しかし、効率至上主義なんて、
散々悩んで考え抜いたことがないと、
仕事のやり方のbefore after を論じることなんて出来ないわけです。
それは、今の事態でも変わらない真理ではあるのだと思うのです。
「おまえらとは、くぐった修羅場の数が違うんだよ」
っていうセリフが
るろうに剣心の齊藤一のセリフにあるんですけどね(笑)、※大好きなので
不器用に遠回りして、おまけに修羅場をくぐり、
ようやく光が見えて
そこからにじみ出てくる、「イシュー」の重要性とありがたみって
経験した人にしかわからないし、活かせないんだろうなと思います。







![BIG tomorrow (ビッグ・トゥモロウ) 2013年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61VyXdwe3eL._SL160_.jpg)

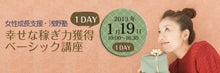



.JPG)
.JPG)

